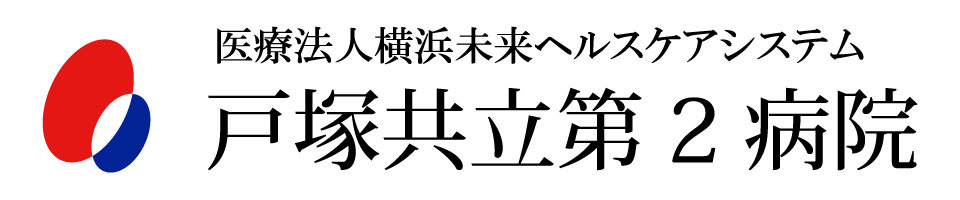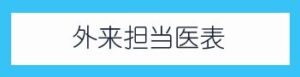「高次脳機能外来」開設のお知らせ
4月より高次脳機能外来を開設いたしました。外来日は、第1週・第3週の火曜日(午前・午後)となります。
主な対象疾患等は以下をご参照ください。
対象となる疾患
- 脳卒中、脳外傷(交通事故、転倒、スポーツ事故等)後の後遺症
高次脳機能障害に対するご相談もお受けいたします
①生活指導
②就労・就学支援
③運転相談
④障害者手帳相談
⑤障害年金相談
⑥診断
高次脳機能障害とは? ~高次脳機能障害の4大症状~
「高次脳機能障害」という言葉は、もともとは学術的な用語で、脳に損傷を受けたことで起こる認知の障害全般を指します。
この中には、次のような障害が含まれます。
-
記憶障害(物事を覚えたり思い出したりするのが難しい)
-
注意障害(集中が続かない)
-
遂行機能障害(計画を立てたり、物事を順序立てて行うのが難しい)
-
社会的行動障害(感情のコントロールができず、対人関係に問題が出る) など
これらの症状により、日常生活や社会生活に制約がある状態が高次脳機能障害です。
高次脳機能障害をもつ人たちには、その障害の特性を踏まえた適切な医学的リハビリテーションや生活訓練、就労・就学支援などが必要であると考えられています。
行政の取り組みと定義
2001年(平成13年度)に始まった国の「高次脳機能障害支援モデル事業」では、多くの脳損傷者のデータが集められ、分析されました。
その結果、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害などの認知障害を抱え、日常生活や社会生活に支障をきたしている人たちがいることが分かりました。
しかし、これらの人たちへの診断方法やリハビリ、生活の支援方法はまだ十分に整っておらず、早急に対策が必要であるとされました。
新たな定義と呼び方
こうした背景から、行政の立場では、これらの認知障害を主な特徴とする障害を「高次脳機能障害」と呼ぶことにし、
その障害を持つ人たちを「高次脳機能障害者」と呼ぶことが適切だとされ、診断基準が設けられました。
担当医
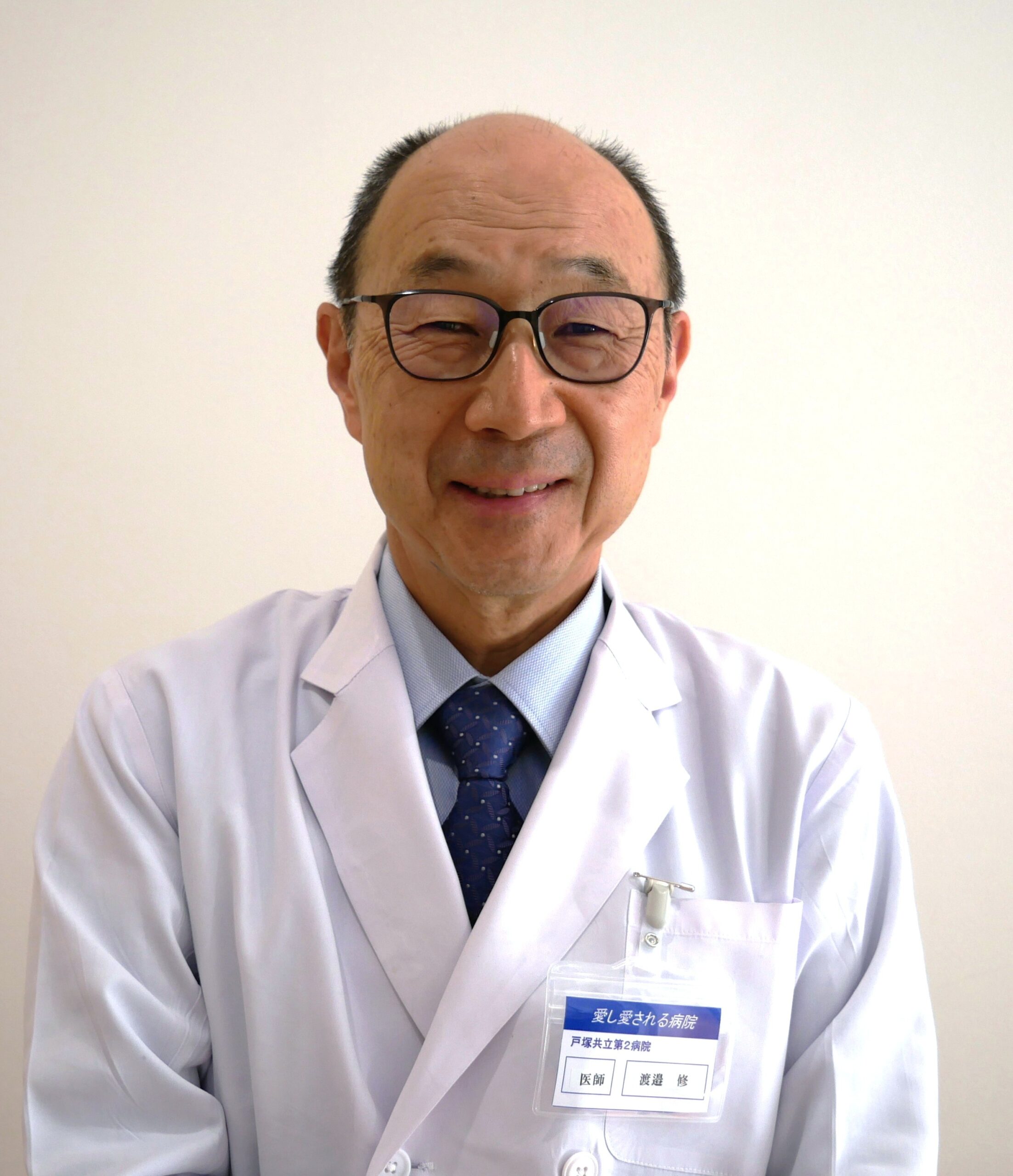
渡邉 修(ワタナベ シュウ)
経歴:
1985年03月 浜松医科大学医学部卒業
1985年05月 浜松医科大学付属病院 脳神経外科配属研究医勤務
1985年05月 浜松医科大学脳神経外科学講座教室 入局
1986年07月 東京厚生年金病院 麻酔科勤務
1987年01月 聖隷浜松病院 脳神経外科勤務
1987年07月 浜松労災病院 脳神経外科勤務
1989年04月 聖隷三方原病院 脳神経外科勤務
1991年04月 浜松医療センター 脳神経外科勤務
1993年04月 東京慈恵会医科大学 リハビリテーション科教室 助手
1993年04月 東京慈恵会医科大学付属第3病院 リハビリテーション科勤務
1994年02月 神奈川リハビリテーション病院 リハ医学科勤務
1995年04月 東京慈恵会医科大学付属第3病院 リハビリテーション科勤務
1995年10年 スウェーデン カロリンスカ病院 臨床神経生理学部門研究生
2000年07月 神奈川リハビリテーション病院 リハ医学科勤務
2005年04月 首都大学東京 教授
2012年04月 東京慈恵会医科大学附属第三病院 リハビリテーション科 診療部長
2013年01月 東京慈恵会医科大学 リハビリテーション医学講座 教授
2025年04月 TMG本部 リハビリテーション医療 特別顧問
資格:
- 日本リハビリテーション医学会専門医、医学博士
- 厚生省 義肢装具等適合判定医
主な学会活動等:
- 日本リハビリテーション医学会代議員、日本交通科学学会理事
- 日本安全運転医療学会理事長、認知神経学会理事、日本高次脳機能障害学会評議員
- 国立障害者リハビリテーションセンター高次脳機能障害情報・支援運営委員会委員
- 東京都高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会委員長
- 日本高次脳機能障害友の会顧問、東京高次脳機能障害協議会顧問
診療スケジュール
【休診・代診一覧】